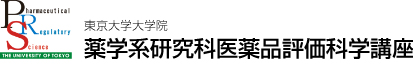第7回医薬品評価科学講座 Intensive Course 終了のご報告
2009年5月30日、東京大学医薬部鉄門講堂に於いて、第7回医薬品評価科学講座 Intensive Course(IC)が開催され、多数の参加者を迎えることができました。
薬物動態の予測と医薬品評価 −予測法をどのように活用するべきか
| 日 時 |
2009年5月30日(土) 10:00〜17:30 |
| 場 所 |
東京大学医学部研究教育棟14階 鉄門講堂 |
協賛 |
日本薬物動態学会/日本製薬医学医師連合会
日本製薬工業協会/日本臨床薬理学会 |
アジェンダ
| 10:00-10:10 |
挨拶・趣旨説明 |
| 10:10-10:35 |
1)FDAトランスポーター薬物間相互作用ガイダンスの現状
(20+5分)
杉山 雄一(東京大学大学院薬学系研究科 医薬品評価科学・分子動態学 教授)
トランスポーター薬物間相互作用とAUC上昇の現状(文献情報)のレビュー。
ガイダンスに向けたFDA Critical Path Transporter Workshop(2008年11月開催)での議論についての解説。 |
| 10:35-11:00 |
2)「薬物相互作用の検討方法について」および今後への展望
(20+5分)
永井 尚美(医薬品医療機器総合機構)
「薬物相互作用の検討方法について」(医薬審発第813号)(2001年)策定に至るまでの経緯・議論。
現在直面している問題点、今後の改善策(特にトランスポーターの関わる相互作用)の説明。 |
| 11:00-11:20 |
3)薬物間相互作用(代謝)の予測(概論)(15+5分)
杉山 雄一(東京大学大学院薬学系研究科 医薬品評価科学・分子動態学 教授)
in vitroデータを用いた薬物間相互作用の予測方法の概説。
製薬産業で待望される相互作用予測シミュレーターの開発状況の報告。 |
| 11:20-11:45 |
4)薬物間相互作用の予測と添付文書記載(20+5分)
鈴木 洋史(東京大学医学部附属病院薬剤部長・教授)
医薬品添付文書における薬物間相互作用の表記(併用禁忌・併用注意)に関する問題点(整合性に欠ける事態、三極で矛盾する表記)の紹介。
臨床試験を行わずにin vivoデータだけで薬物間相互作用の動態変化を予測する方法の紹介。
添付文書記載のあり方についての提案。 |
| 11:45-13:00 |
昼休み |
| 13:00-13:20 |
5)PGxと多型と薬物体内動態の予測(15+5分)
前田 和哉(東京大学大学院薬学系研究科 分子薬物動態学 助教)
代謝酵素・トランスポーターの遺伝子多型が、どんな時に薬物動態・薬効・副作用に影響を与えうるか?
薬物動態の個体差・人種差に及ぼすインパクトは?
野生型アレル保持者の薬物動態パラメータをもとに、臨床試験を行わずして変異アレル保持者の薬物動態を予測する方法は? |
| 13:20-13:40 |
6)「臨床研究に関する倫理指針」の改正について(15+5分)
栗原 千絵子
(放射線医学総合研究所 分子イメージング研究センター運営企画ユニット 臨床研究支援室 主任研究員、医薬品開発支援機構)
「臨床研究に関する倫理指針」の改正(平成20年厚生労働省告示第415号;平成21年4月1日より施行)のおもな変更点の解説。 |
| 13:40-14:10 |
7)PGxや動態とレギュレーション(25+5分)
石黒 昭博(医薬品医療機器総合機構)
PGxの扱いに関するPMDAやFDA、EMEAの動向の紹介
ゲノムバイオマーカーをめぐるICHガイドラインにむけた動向の解説
審査のみならず市販後安全性管理におけるPGx、PPK、PK/PDの応用可能性、PMDAの見解の説明。 |
| 14:10-14:50 |
総合討論 40分 |
| 14:50-15:10 |
休憩 |
| 15:10-15:35 |
8)ヒトでの代謝物を用いた毒性試験(20+5分)
池田 敏彦(横浜薬科大学教授、東京大学大学院薬学系研究科特任教授、医薬品開発支援機構理事)
ヒトでの代謝物がある場合はその毒性試験を要求する、というFDAのガイダンス
(FDA Guidance for Industry; Safety Testing of Drug metabolites (February 2008))の内容と問題点の解説。 |
| 15:35-16:00 |
9)バイオマーカーとしてのPETプローブの利用に関するガイダンス作成の必要性(20+5分)
矢野 恒夫(理化学研究所分子イメージング科学研究センターコーディネーター、 医薬品開発支援機構理事)
PETプローブなどをメディカルイメージング剤という新しい概念で実用化する、FDAガイダンス(Developing Medical Imaging Drug and Biological Products (June 2004))の内容を解説。
疾患特異的バイオマーカーをPETプローブによって画像化して、薬効を評価するサロゲートエンドポイントや受容体占有率による投与量推定に活用する。臨床試験全般に関する問題点の整理、およびガイダンスの必要性についての提案。 |
| 16:00-16:20 |
10)バイオアベイラビリティの予測とレギュレーション
(15+5分)
今若 治夫(小野薬品工業株式会社研究本部 プロジェクト推進部)
『医薬品の臨床薬物動態試験について』の通知(H13年6月1日制定)で経口投与製剤においても静脈内投与試験を実施し、バイオアベイラビリティ(BA)を求めることを推奨されたが、その現状の説明。
ヒトBA予測法の紹介。 |
| 16:20-16:45 |
11)In silicoのADME予測とレギュレーション(20+5分)
草間 真紀子(東京大学大学院薬学系研究科 医薬品評価科学 助教)
実測データを使わずに、構造式のみで予測可能な数個のパラメーターのみでヒトにおけるクリアランス特性を予測する方法の紹介。
その方法論を医薬品開発やレギュレーションに対する応用可能性の提案。 |
| 16:45-17:30 |
総合討論 45分 |
★ポスター(PDF)はこちら
東京大学大学院薬学系研究科
医薬品評価科学講座
TEL:03-5800-6988
FAX:03-5800-6949
PRS事務局
Email